「世界遺産って、なんだかロマンがあるな」
そう思って検定を受けてみようと思った方、きっと少なくないのではないでしょうか。
私が世界遺産検定に興味を持ったのは、何度も海外を旅してきた中で、「歴史や文化の背景を知らずに見ていたのは、ちょっともったいなかったかも…」と感じたことがきっかけでした。
検定を受けることで、遺産に込められた意味や物語を知ることができ、旅の楽しみ方もぐんと深まります。
そんな学びの第一歩として、私は「世界遺産検定2級」に挑戦しました。
3級は一夜漬けでなんとか受かったものの、内容はほとんど記憶に残らず…。やはり2級からが本番だと実感しています。
この記事では、2級に合格するまでの体験をもとに、出題範囲や学習のコツをわかりやすくまとめました。
これから受験を考えている方や、興味を持っている方の参考になれば嬉しいです。
目次
まずはここから!世界遺産検定2級ってどんな試験?
世界遺産検定2級は、「世界遺産について幅広い知識を持ち、背景となる歴史や文化も理解しているか」を問うレベルです。
検定には1級・準1級・2級・3級・4級といった段階がありますが、2級から本格的に学習のボリュームが増えてきます。
試験概要
- 問題数:全60問(マークシート式・4択)
- 試験時間:60分
- 合格ライン:60点以上(100点満点)
- 受験方法:会場またはオンライン受験(※私はオンラインで受けました)
世界遺産検定2級公式テキスト「くわしく学ぶ世界遺産300」が対象となり、範囲はかなり広めです。テキストは全部で39章あり、文化遺産・自然遺産に関する知識から、歴史・宗教・建築・用語の理解まで、多岐にわたります。
いきなりすべてを網羅しようとすると、途方もないように感じるかもしれません。でも大丈夫。
出題の傾向には“ちょっとした偏り”があるので、まずはそれを押さえることで、効率よく勉強が進められます。
次は、その出題傾向と配分についてご紹介しますね。
出題の55%はここから!まず押さえるべき基礎知識と日本の遺産
世界遺産検定2級の出題範囲はとても広く、公式テキストでは全部で39の章に分かれています。
ですが、いきなり全部に手をつけようとすると、どこからどう勉強すればいいのか迷ってしまいますよね。
そんなときに目安になるのが、出題傾向とジャンルごとの配分です。
まず最初に押さえておきたいのは、出題の約55%が「基礎知識」と「日本の遺産」から出るという点です。
基礎知識だけで約25%
「世界遺産とは何か?」「登録の仕組みは?」「遺産の種類は?」といった、検定の土台となる知識は必ず出題される超重要分野。
このパートだけで**全体の約25%**を占めるため、テキストの最初の方だからといって流し読みせず、しっかり理解しておきたいところです。
特に、以下のようなテーマは頻出です。
- 世界遺産条約とその背景
- 登録の基準(文化遺産・自然遺産・複合遺産)
- 保護や管理の仕組み
- 関連する国際機関や用語(ICOMOS、IUCNなど)
仕組みや制度は少しとっつきにくい部分もありますが、表にまとめたり、図で整理すると一気に覚えやすくなります。
私はここでChatGPTを使って、図や用語の整理をしてもらっていました。
日本の遺産は全体の約30%!過去問対策もしやすい
日本の世界遺産は、文化遺産・自然遺産あわせて20件以上(2024年時点)。
国内の遺産は馴染みがある分、イメージがしやすく覚えやすいというメリットもあります。
出題も**約30%**と高く、ほぼ毎回登場する定番分野。テキストの記述に加えて、最近登録された遺産や、拡大登録された背景などにも注目しておくと、応用問題にも強くなります。
世界の遺産では文化遺産の出題が多め
世界遺産の大半は文化遺産であるため、検定でも文化遺産の出題がやや多めです。
とはいえ、自然遺産や複合遺産ももちろん出題されるので、「文化:自然=7:3」くらいのイメージでバランスよく学習するのが理想です。
「まずは配分の大きいところから、確実に取れるようにする」
これが合格への第一歩になります。
次の章では、実際にどんな分野から問題が出されているのか、テキストの構成と出題傾向を整理してご紹介します。
世界遺産を6つのテーマで分類しよう!
公式テキスト『くわしく学ぶ世界遺産300』は、全部で39チャプター。内容は多岐にわたり、世界各地の遺産が紹介されています。ただ、そのまま学び始めると「どこから手をつけたらいいの?」と迷ってしまうことも。
そこで私は、この39章を学習効率と出題傾向に合わせて、ざっくり6つのテーマに分けてみました。分類の仕方はあくまで一例ですが、自分の得意・苦手分野を把握するのにも役立ちます。
6つの分類はこちら:
- 世界遺産の基礎知識
― 世界遺産ってどうやって登録されるの?文化遺産と自然遺産の違いって?そんな素朴な疑問に答えてくれる、いわば“土台”となるテーマです。 - 日本の遺産
― 私たちの住む日本にも、たくさんの世界遺産があります。法隆寺や白川郷、富士山など、身近だからこそ深く知りたい遺産たちが勢ぞろい! - 歴史都市・建築・文化的景観
― ヨーロッパの古都、イスラムの町並み、アジアの伝統建築…人類が築いてきた街や建物の美しさに触れるテーマです。 - 宗教と古代文明 ― 世界の宗教や古代文明、文化交流、そして戦争や奴隷制度など負の歴史を伝える遺産。
- 文化交流・産業・負の遺産
― 大航海時代の港町、シルクロード、産業革命の工場群、そして戦争や奴隷制度の記憶を伝える「負の遺産」まで。人類の交流と発展、そして教訓が詰まったテーマです。 - 自然遺産と地球の歴史
― 地球の大自然が生んだ絶景たち。火山、氷河、サンゴ礁、熱帯雨林…生き物たちの命の営みと、地球の壮大な歴史が感じられるテーマです。
この6つに分けると、自分がどの分野に強いのか、またどこを重点的に学習すべきかが見えてきます。もちろん、テキストではこれらのテーマが混ざり合うように構成されているので、章の並び順そのままではありません。
次の章では、それぞれのテーマにどの章が含まれるのか、さらに詳しく説明していきますね。
出題ジャンルを徹底解説!~6つのテーマで世界遺産を理解しよう~
世界遺産検定2級のテキスト『くわしく学ぶ世界遺産300』は、全39章で構成されています。これらを理解しやすくするために、前章では6つのテーマに分類しました。この章では、その6テーマそれぞれについて、どんな内容が扱われているのかを詳しくご紹介します。
各ジャンルには、関連する章番号と章タイトルも記載しているので、「このジャンルの勉強を進めたい!」と思ったときに、すぐに該当の章にアクセスできます。また、今後各ジャンルの代表的な遺産やキーワードをまとめた記事も予定していますので、併せてご活用ください。
1. 世界遺産の基礎知識
- CHAPTER 1 世界遺産の基礎知識
世界遺産検定2級を受けるなら、まずはここが土台!
このチャプターでは、世界遺産とは何か? どんな種類があるのか? どうやって登録されるのか?――といった「世界遺産のルールブック」のような知識がまとまっています。
たとえばこんな内容が登場します:
- 世界遺産には「文化遺産」「自然遺産」「複合遺産」の3種類がある
- ユネスコの「世界遺産条約」ってどんなもの?
- 登録までのプロセス(暫定リスト・推薦書・諮問機関など)
- 「真正性」「完全性」ってなに?
- 危機遺産や抹消の仕組み
こうした用語や制度に関する知識は、2級でもバッチリ出題されます。世界の遺産を楽しく知るための前提となる部分なので、しっかり押さえておきたいところです。
検定対策としても、ここを理解しておくと、他のチャプターで出てくるキーワードがすんなり頭に入ってきますよ!
2. 日本の遺産
- CHAPTER 2 日本の遺産
世界遺産検定で日本の遺産は、やはり外せない重要テーマ!
このチャプターでは、日本にある世界遺産すべてがまとめられていて、検定でも毎回必ず出題される超頻出ジャンルです。
日本の遺産は文化遺産・自然遺産あわせて20件以上ありますが、それぞれが独自の歴史や文化、自然環境をもっています。
例えばこんな遺産が登場します:
- 法隆寺地域の仏教建造物(奈良県):現存する世界最古の木造建築群!
- 古都京都の文化財(京都府など):清水寺や金閣寺など、古都の美がぎゅっと詰まってます。
- 富士山-信仰の対象と芸術の源泉(山梨県・静岡県):自然遺産ではなく、文化遺産として登録されているのがポイント。
- 屋久島(鹿児島県):縄文杉で有名な、日本が誇る自然遺産の代表格。
- 北海道・北東北の縄文遺跡群:新しく加わった文化遺産として注目!
また、日本の遺産には「シリアル・ノミネーション(複数の構成資産)」が多いのも特徴のひとつ。どの構成資産が含まれているかなども、検定ではよく問われるポイントです。
日本の歴史や自然を世界がどう評価しているのか――という視点で見ていくと、普段の旅行先やテレビで見る景色も、もっと面白くなりますよ!
3. 歴史都市・建築・文化的景観
- CHAPTER 4 文化的景観
- CHAPTER 5 シリアル・ノミネーション/トランスバウンダリー
- CHAPTER 7 歴史地区と旧市街
- CHAPTER 8 都市計画
- CHAPTER 20 ヨーロッパの建築様式
- CHAPTER 21 近現代建築
このテーマでは、街並みや建築様式、人々の暮らしと調和した「文化的景観」など、人間の歴史と空間が融合した遺産を学びます。
都市の成り立ちや建築の進化を知ると、世界中の街歩きがもっと楽しくなります!
例えばこんな世界遺産が登場します:
- ローマの歴史地区(イタリア):古代から中世、近代までの建築が一堂に会する“生きた博物館”のような街!
- ブルッヘの歴史地区(ベルギー):中世の街並みがそのまま残る、美しい運河都市。
- ヴィースの巡礼教会(ドイツ):ヨーロッパ建築のバロック様式の傑作。
- バウハウス関連遺産(ドイツ):モダンデザインの原点ともいえる近現代建築が評価された例。
- ブールゴン渓谷のワイン産地の文化的景観(フランス):ワイン文化と景観の調和が見どころ。
また、「文化的景観」や「シリアル・ノミネーション」など、世界遺産登録の仕組みとしても重要なキーワードが頻出。
これらは検定でもしっかり問われます。
文化と空間が織りなす美しい世界をめぐるこのテーマ、旅行好きにも建築好きにもおすすめのジャンルです!
4. 宗教と古代文明
- CHAPTER 3 世界で最初の世界遺産
- CHAPTER 6 文化の多様性
- CHAPTER 9 キリスト教(カトリック/プロテスタント)
- CHAPTER 10 キリスト教(正教会/東方諸教会)
- CHAPTER 11 イスラム教
- CHAPTER 12 仏教
- CHAPTER 13 世界の宗教
- CHAPTER 14 古代ギリシャとヘレニズム
- CHAPTER 15 ローマ帝国
- CHAPTER 16 先史時代
- CHAPTER 17 古代文明
- CHAPTER 18 アメリカ大陸の文明
- CHAPTER 19 東南アジアと南アジア
このテーマでは、宗教・神話・古代文明といった人類の根源的な文化が育んだ世界遺産を見ていきます。
歴史の授業で聞いたことのある名前が続々と登場し、「あの時代ってこうつながってたんだ!」と気づきが多いはず!
たとえば、こんな世界遺産があります:
- アテネのアクロポリス(ギリシャ):古代ギリシャ文明の象徴、パルテノン神殿で有名ですね。
- ローマの歴史地区と教皇庁関連建造物(イタリア・バチカン):キリスト教の歴史と結びついた壮大な遺産群です。
- マチュ・ピチュ(ペルー):インカ文明の神秘に触れられる、雲の上の都市。
- カジュラーホの寺院群(インド):ヒンドゥー教建築の粋を集めた彫刻美術が圧巻!
- ストーンヘンジ(イギリス):先史時代の巨大な謎、誰がなぜ建てたのか…興味は尽きません。
また、世界三大宗教や多神教、シャーマニズム、土着信仰など宗教の多様性も大きなテーマ。
宗教の違いを学ぶことで、文化への理解がより深まるジャンルでもあります。
古代の叡智と信仰が形になった、壮大な人類の“遺産図鑑”を旅するようなテーマです!
5. 文化交流・産業・負の遺産
- CHAPTER 22 十字軍と騎士団
- CHAPTER 23 大航海時代とキリスト教の海外布教
- CHAPTER 24 商業・交易・貿易
- CHAPTER 25 混ざり合う文化(文化
- CHAPTER 26 近代国家
- CHAPTER 27 産業遺産
- CHAPTER 28 未来への教訓
このテーマでは、世界各地の文化が交差し、影響しあった歴史や、産業革命の足跡、そして戦争や奴隷制といった負の歴史を伝える世界遺産を扱います。
ひとことで言うと、「人類の歩んできた光と影」が感じられるテーマです。
たとえば、こんな世界遺産が登場します:
- グアラニーのイエズス会布教施設群(アルゼンチン、ブラジル):宗教布教と植民地政策が交差した、南米の歴史の一幕。
- リヴァプールの海商都市(イギリス・登録抹消):交易と産業の中心だった港町。負の側面も含めて学ぶ価値があります。
- 石見銀山遺跡とその文化的景観(日本):世界に銀を送り出した日本の鉱山遺産。環境との共存も見どころ。
- アウシュヴィッツ・ビルケナウ(ポーランド):ホロコーストの記憶を伝える「負の遺産」として知られています。
- 八幡製鉄所関連施設(日本):近代日本の産業発展の象徴的存在です。
文化が混ざりあうことで生まれた独自の景観や、産業の発展の裏にあった苦労と犠牲…。
過去に目を背けず、きちんと向き合うことで、世界遺産の価値をより深く理解できるテーマです。
6.自然遺産と地球の歴史
- CHAPTER 29 地球の歴史
- CHAPTER 30 カルスト地形
- CHAPTER 31 氷河地形
- CHAPTER 32 湖・湿地帯
- CHAPTER 33 森林・熱帯雨林
- CHAPTER 34 草原
- CHAPTER 35 火山
- CHAPTER 36 化石出土地帯
- CHAPTER 37 固有の生態系
- CHAPTER 38 海洋生態系
- CHAPTER 39 絶滅危惧種
このテーマでは、自然の力や地球の歴史、そしてそこに生きる命の多様性を学びます。
「文化遺産」とはちょっと違って、地球そのものの姿を楽しめるのが最大の魅力です。
登場する世界遺産には、地形・生態系・地球の成り立ちを感じさせるものばかり。
たとえば…
- ヨセミテ国立公園(アメリカ):氷河によって削り取られた壮大なU字谷と断崖が有名です。
- シュンドルボン(バングラデシュ/インド):ベンガルトラが生息する世界最大のマングローブ林。
- ハロン湾(ベトナム):カルスト地形が海から突き出す、幻想的な景観。
- イエローストーン国立公園(アメリカ):地熱活動が活発な火山地帯で、世界初の国立公園でもあります。
- グレート・バリア・リーフ(オーストラリア):世界最大のサンゴ礁は、気候変動の影響を受けながらもその美しさを保っています。
また、「化石出土地帯」や「絶滅危惧種」といったチャプターでは、地球46億年のドラマや生物多様性の危機についても考えさせられます。
「世界って、なんて広くて美しいんだろう…」と感じること間違いなし。
知的好奇心と自然へのリスペクトが深まる、そんなテーマです!
まとめ ~出題範囲と傾向を押さえて、効率よく学ぼう~
世界遺産検定2級では、公式テキスト『くわしく学ぶ世界遺産300』全39章から幅広く出題されます。試験に合格するには、単に暗記するのではなく、出題傾向や分野ごとの配分を意識して効率よく学ぶことが大切です。
特に重要なのは以下の3点です:
- 基礎知識と日本の遺産だけで全体の約55%を占める
→ この2ジャンルを優先的に学習するだけでも得点源になります。 - 世界の遺産は6つのジャンルに整理して理解するのがカギ
→ 地域やテーマごとの特徴を押さえることで、混乱を防げます。 - 文化遺産が中心に出題されるが、自然遺産の基本分類や保護の視点も見逃せない
→ 全体のバランスを意識しつつ、頻出分野を重点的にチェックしましょう。
この記事では、全39章の出題範囲を6つのジャンルに分類し、それぞれの構成章や特徴を詳しく解説しました。今後は、各ジャンルごとのキーワードや代表的な遺産を整理した記事も公開予定ですので、そちらもあわせて活用していただければと思います。
世界遺産の学びは、単なる試験対策を超えて、地球と人類の歴史を深く知る旅でもあります。楽しみながら、知識を広げていきましょう!



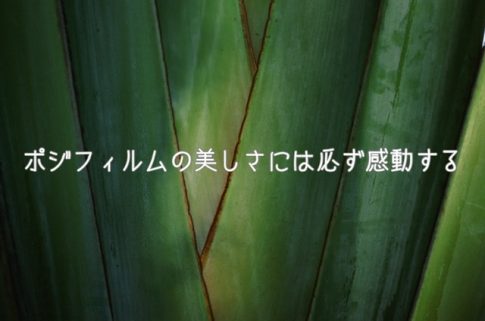
コメントを残す